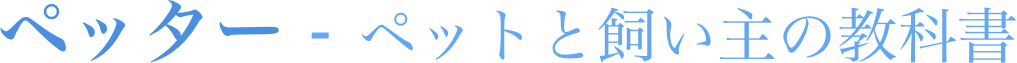猫も年を取ると人と同じように加齢臭がするようになります。
長生きをすると仕方のないことではありますが、きちんとした対策を取れば、この臭いも最小限に抑えることができます。
ここでは、年とともに増していく老猫の加齢臭の対策方法をご紹介します。
温度と湿度を管理する
加齢臭をおさえるには、まず老猫を健康に保ってあげることが一番大切です。
普段の生活で老猫が一番長く過ごす場所の温度や湿度を調節し、老猫にとってその空間が居心地のよい状態になるようにしましょう。
老猫の生活環境を整えることは、臭いの原因になる病気にかかりにくい体づくりにつながります。
老猫にとって快適な空間は、温度23~28度、湿度は50~60%です。
エアコンで調節すれば手軽ですし悪いことではありませんが、直接エアコンの風が体に当たったり乾燥しすぎてしまうと逆効果になってしまいます。
保温効果のあるアルミシートや、ペットショップで販売している冷却効果のあるマット等も同時に利用すると良いでしょう。
老猫の負担を減らすだけでなく、電気代の節約にもなります。
また日当たりの良い場所に寝床を作ってあげれば、体の殺菌効果も同時に得られます。
健康を保つためにも、室内は老猫にとって過ごしやすい環境を保つようにしましょう。
できるだけ体を清潔に保つ
柔軟性の高い猫も年を取ると体が硬くなり、若い時のように自分の体を隅から隅までグルーミングすることができなくなります。
自分でキレイにできなくなってしまった体に付いた汚れは、飼い主が取り除いてあげる必要があります。
食べカスや尿などが体に付いたままだと、加齢臭の原因になるだけでなく衛生面でも大きな問題になります。
肛門の周りや食べカスがついたままになりやすい口の周り、アゴ下、垢のたまりやすい耳の中、また汗腺のある肉球は臭いの強くなりやすい部分です。
こまめにチェックして清潔に保ちましょう。
高齢の猫には、シャンプーは体力を消耗し負担になることもあります。
シャワーやお風呂が嫌いな猫や体力のない老猫は無理にお風呂に入れなくても大丈夫です。
水なしで使えるシャンプーを利用したり、ブラッシングとあわせて温かい蒸しタオルで体を優しく拭いてあげると良いでしょう。
また、体だけでなく口内もチェックしてみましょう。
虫歯や口内炎も臭いの原因になります。
口内のトラブルを予防するために、綿棒やペット用の歯磨きグッズを使って歯を磨いてあげましょう。
日ごろから老猫の体のメンテナンスを心がけると体調の変化に気づきやすくなり、病気の早期発見にも繋がります。
消化しやすいエサを与える
猫も年を取ると消化器官が衰えていきます。
老猫に対して今までと同じエサを与え続けると内臓に負担がかかり、消化不良を起こして口臭が強くなってしまいます。
口臭が強くなった、肛門周辺の臭いが強いと感じたら、高齢猫用のキャットフードに変えてあげましょう。
高齢猫用のキャットフードは、成猫用ドライフードと比べて粒が小さく作られています。
あるいは、ウエットフードなら細かく刻まれていたりと、消化機能の衰えた老猫にも消化吸収しやすいよう工夫されています。
老猫用フードが手に入らない場合は、フードを細かく砕いたりお湯でふやかして与えると老猫にも消化しやすくなります。
また、キャットフード以外に人の食べ物を分けて与えるのもやめましょう。
人の食べ物を与えると加齢臭が強くなるだけでなく、糖尿病や他の病気を引き起こす原因にもなります。
美味しそうに食べていても、塩分の多い人の食べ物は老猫の肝臓に大きな負担を与えます。
加齢臭が増すだけでなく重篤な病気を誘発しかねません。
病院で診てもらう
上記の対策を取っているにもかかわらず、あまりにも加齢臭が強い時は、一度病院で検査してもらうとよいでしょう。
虫歯や腎不全からくる口内炎、その他の病気や怪我により臭いが強くなっているのかもしれません。
加齢臭の他に変わった様子がないかよく観察し、獣医さんに相談してください。
獣医さんに連れていかれることは、猫にとって大きなストレスになりかねないことです。
病院に慣れさせるためにも、若く健康なうちから定期的に診断に通って病院に慣れさせておくと、いざという時に猫への負担が少なくなります。
また、老猫はウイルスに対する抵抗力も弱くなっています。
病院に連れていく時は、できるだけ移動に時間のかからない病院へ、混雑時を避けて来院すると良いでしょう。
猫も年を重ねると病気にかかりやすくなります。
飼い猫が7~8歳を過ぎたら、できれば半年に一度、少なくとも1年に一度は定期的に病院で検診してもらうとよいでしょう。
猫の加齢臭の対策方法を知ろう
加齢臭は、体の衰えや病と密接なつながりがあります。
加齢臭の対策は臭いを抑えるだけでなく、病気の早期発見や老猫の健康を保つことにもなります。
猫の加齢臭にはしっかりと対策をして、大切な家族の健康を守ってあげましょう。