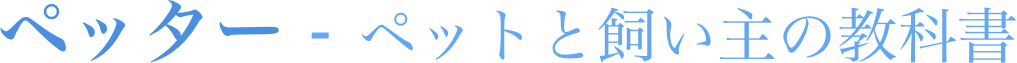猫の食事を与える場合、一日のうち決まった量を決まった回数で与える場合と、お皿にだしっぱなしにする方法があります。
だしっぱなしにすることを置き餌と言います。
だしっぱなしにすることでどういったメリットやデメリットがあるのでしょうか。
衛生的な問題
だしっぱなしにすることで生じる問題点の一つとして衛生面があります。
一度猫が口をつけたフードは、猫の唾液などからついた雑菌が繁殖してしまいます。
水分の多いウェットフードであれば、雑菌の繁殖はより多いものになってしまいますし、ドライフードであってもウェットフードよりは少ないものの雑菌の繁殖は免れません。
これは季節を問わず気を付けていただきたい点です。
夏は気温や湿度、冬であっても暖房や加湿器により、温度と湿度は菌に対しても快適な環境を与えてしまいます。
飼い主さんの食事を冷蔵庫に入れずに一日中テーブルに置いておくことを考えると、ちょっと心配になりますよね。
フードの酸化
キャットフードはほとんどの場合、原材料にお肉やお肉の油が使われています。
食物アレルギー用としてお肉が一切使用されていないものもあります。
お肉やお肉の油は、猫が生きていく上で必要となる栄養をキャットフードから摂る必要があるため、また猫の食いつきを良くするためのものです。
お肉の脂肪分や油は空気に触れることで酸化してしまいます。
原材料の中には酸化をしないように酸化防止剤が添加されていますが、その効果は開封前の話。
キャットフードをお皿に入れて置いておくと、空気中の酸素に反応してドンドンと酸化が進んでしまいます。
その食事を摂り続けることにより猫の健康に悪影響を与えてしまうことになります。
空気に触れさせ過ぎないことはもちろんのこと、さらに言えば一度開封したキャットフードは何食分かに小分けにしてジッパー付きの袋に入れ、脱酸素剤(シリカゲルなど)を袋の中に入れておくと、開封後も酸化が進みにくくなります。
食事量の把握が難しくなる
猫の健康状態を測る一つの手法として食事量の管理があげられます。
キャットフードのパッケージの多くには、猫の年齢や体重に合わせた一日あたりの給餌量が記載されています。
これは猫が快適な生活を送る上で必要なカロリーや栄養素が設定されています。
だしっぱなしにすることで、猫がいつ、どのくらいの量を食べたのか把握できなくなり、食欲の増減や健康チェックができなくなります。
また、一頭だけではなく二頭以上の多頭飼育をしている場合は、誰がどれだけの量を食べたのかがさらに把握できなくなります。
食事は健康のバロメーターです。
きちんと食事ができているかを見ることも飼い主さんの大事な役割です。
処方された食事について
何かしらの健康トラブルを抱えている場合、動物病院で治療のために処方されるキャットフードを与える場合があります。
こういったキャットフードを処方食、あるいは療法食と言います。
基本的に治療のための食事なので、抱えているトラブルが完治すれば通常の食事に戻ることになります。
しかし、病気の症状によってはずっと与え続けなければならないこともあります。
あくまで治療による一環の食事ですので、与えるエサの量の管理はもちろん、動物病院での経過観察も必要となってきます。
多頭飼育をしていて、そのうちの一頭だけが処方食を食べなければならないとき、食事をだしっぱなしにすると誰がその処方食を食べたのか、本来食べなければいけない猫が、食べることができたのかの把握ができなくなってしまいます。
猫の食性に合っている
最後にキャットフードを出しっぱなしにするメリットになりますが、猫の本来の食性は一日に複数回に分かれています。
猫が自然界で食事をする際、ネズミなどの小さな獲物を捕らえて食事をしますが、生きるのに必要となる一日の食事量を満たすためには、何度も狩りをし、捕らえなければなりません。
だしっぱなしにするということは、一日に何度も分割して食事ができるため、猫の本来の食性に合っていると言えます。
また、ペットとして飼われている猫に関しては、飼い主さんの生活パターンによっても変わってきます。
猫を飼われているご家庭で、日中誰かしらが家にいる場合は良いのですが、全員が出かけていたり一人暮らしをされている方の場合、猫に食事を与える人がいません。
何回か分割して食事ができるよう、自動給餌器もオススメです。
キャットフードをだしっぱなしにするメリットとデメリットを知ろう
猫の食性に合わせることも大事ですが、衛生面や健康面に配慮してあげることも飼い主さんの大事な役割になります。
一日に何回か設定して食事を与えることができる自動給餌器で食事ができるようにしておくのがベストでしょう。
ただ飼い主さんの生活パターンもあります。
だしっぱなしのデメリットだけにとらわれず、数時間から半日、半日から一日といったリズムで食事の量と回数を調整してみましょう。