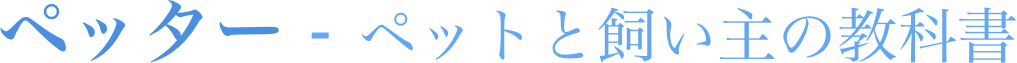年をとり病気にかかりやすくなった老猫には、肥満はもちろん痩せすぎも健康に良くありません。
老猫に負担がかからない工夫をして、適正な体重を維持してあげましょう。
ここでは、消化機能が衰えて食の細くなった老猫でも無理なく体重を増やせる方法をご紹介します。
好物を多めにあげる
猫用のおやつや鰹節、匂いの強い加工食品などの猫が好む食べ物は、カロリーや塩分量が高いためあまり大量に与えて良い物ではありません。
しかし、適切な量を上手に利用できれば、老猫の食欲を増進させるうえで大いに役立ちます。
猫も年をとると人間と同じように様々な感覚が衰えていきます。
嗅覚もその一つです。
いつものフードに猫の好物を多めに足してあげてください。
猫用おやつや海苔、鰹節などの食品は、普段のキャットフードより匂いが強く、嗅覚の衰えた老猫の食欲を刺激してくれます。
煮干しや海苔等の匂いの強い食べ物をいつものフードにかけたり、茹でたささみ肉のような食感の良い食べ物を加えてあげましょう。
年をとった猫でも食事を楽しむことができます。
この方法なら、老猫にストレスを与えずに体重を増やしていく事ができます。
ただし、腎臓疾患や糖尿病等の病気を抱えている猫にはこの方法は適していません。
病気を悪化させ、老猫の体により多くの負担をかけてしまいます。
もし老猫に何か持病があるなら、かかりつけの獣医さんに相談し、老猫の健康状態を考慮して行いましょう。
消化しやすいものをあげる
食べ物の好き嫌いに偏りがあったり、警戒心が強く頑固な猫の中には、決まったエサ以外を受け付けない猫もます。
その場合は、いつものフードを細かく砕く等、消化吸収しやすいよう加工してあげてください。
消化機能が衰え、歯も弱くなってしまった老猫には、食事にかかる負担を減らす事が、体重の増量に繋がります。
今まで与えていたフードを変えなくても、ちょっとした工夫で老猫でも十分に栄養が摂取できます。
他の物は食べないからとあきらめず、いつものエサが老猫の状態に適しているか観察してみてください。
粒が大きすぎる、固すぎるなどの問題点を探しましょう。
柔らかいウエットフードでも、身をほぐしてあげるだけで猫の食いつきが良くなるかもしれません。
ドライフードを軽く砕いた後、さらにお湯をかけてふやかしてあげるとより消化しやすくなり、老猫の胃への負担を減らすことができます。
また、猫は温かい食べ物を好むので、フードにお湯をかけると食欲の増進にも繋がります。
お湯の代わりに香りのよいだし汁や温めた猫用ミルクも効果的です。
お湯でふやかしたフードは、そのままのものより腐りやすくなります。
老猫が食べるのをやめてしばらくしたら、残ったエサはそのままにせずにその都度捨ててください。
ペットがお腹を壊す原因になります。
専用のキャットフードをあげる
いつもと同じキャットフードの銘柄でも、売り場をよく見ると子猫用、成猫用、老猫用等いろいろな種類があることに気づくでしょう。
猫の体重が減ってきた、食欲が落ちたと感じたら、成猫用から老猫用のキャットフードに変えてあげましょう。
老猫用キャットフードの特徴は製品によって様々です。
成猫用より粒を小さくしていたり、高たんぱくな物、脂質の多い物といった様々な特徴があります。
基本的に成猫用のキャットフードより栄養価は高く作られているので、体重を増やしたい老猫の好みや体調に合わせてフードを選ぶと良いでしょう。
動物病院によっては、退院後や手術後、そして消化機能の衰えた老猫に適した栄養価の高いフードを取り扱っています。
一般的なフードより割高ですが、添加物も少なく、消化吸収に関しても考慮されているので持病のある老猫にも安心して与えられます。
持病や手術経験のある猫なら、体への負担を減らすためにも一度病院のフードを考えてみてください。
こまめにあげる
健康な若い猫には、一般的に一日2回に分けてエサを与えます。
胃も小さくなってきた老猫は、一度に食べられるエサの量も若い時より少なくなっています。
胃の大きさに合わせて一度に与えるエサの量を減らし、食べられる量をこまめに与えた方が沢山の量を食べられ、無理なく体重を増やせます。
一日の食事の回数は、一日に与えるエサの量が適切になっていれば何度に分けても構いません。
猫の体重や年齢に合わせ、個々のキャットフードに記載されている通りの量を目安にしてください。
あらかじめキャットフードを一日分ずつに分けて保存袋に入れておくと食べた量も確認しやすく便利です。
キャットフードを小袋に分けてポケットに入れておけば、猫の気が向いた時に2~3粒ずつ与えることもできます。
老猫の体重が回復しない時は病院へ
上記の方法を試しても食欲がなかったり、いくら食べていても体重が増加しない場合は、腎不全や糖尿病といった重篤な病気の可能性が考えられます。
これらの病は早期発見して悪化を食い止める必要があります。
できるだけ早く獣医さんに診てもらいましょう。