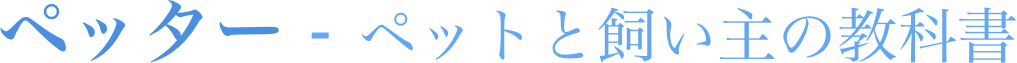猫はむかしから人の暮らしに密接に関わりをもつ動物でした。
よく「犬は人につき、猫は家につく」と言いますが、これは猫を飼ったことのある人にはよく実感されていることだろうと思います。
そんな猫はまた、俳句の中でも詠まれてきました。
今回は、猫の登場する俳句をご紹介します。
猫逃げて 梅ゆすりけり 朧月(池西言水)
季語は朧月で、季節は春です。
猫逃げて、とあるところをみると偶然鉢合わせしたノラ猫が逃げてゆくような場面でしょうか。
ノラ猫と飼い猫との反応の違いは、路地裏を散歩しているときなど、町中で猫を見かけたときによくわかるところです。
その逃げる過程で梅の木に登ったのでしょう、梅の枝が揺れています。
その梅の木の空には、春の朧月がある―そんな俳句です。
視線が逃げてゆく猫、揺れる梅、空の朧月と移動していることがわかります。
猫が逃げてしまった後の一抹の寂しさを感じる俳句です。
猫の子に 嗅がれているや 蝸牛(椎本才麿)
季語は蝸牛で、季節は夏です。
猫の子がカタツムリのにおいを嗅いでいる、というただそれだけを詠んだ俳句ですね。
猫の子は、非常に好奇心が旺盛でなんでもよくにおいを嗅ぎます。
嗅がれているカタツムリも、おそらくは気づいていない様子です。
殻からでてきて身体も目玉も伸びきったところを嗅がれている、そんな趣でしょう。
成長しても猫同士の挨拶に、鼻を近づけあい、においを嗅ぐような仕草を見せますね。
それにしても猫はよく、においを嗅ぎます。
猫に限らず動物にとっては嗅覚も大切な情報のひとつ、ということでしょう。
われわれ人間はどこか等閑にしているような、そんな気持ちにもなります。
ねこの子の くんずほぐれつ 胡蝶哉(宝井其角)
季語は胡蝶で、季節は春です。
猫の子が勢いよく蝶にとびかかっていく様が目に浮かんできます。
この季節特有の青々とした春の草の上を跳び上がって蝶に手を伸ばしている子猫の姿は、滑稽さもあり、また生命力にあふれています。
蝶もまた、咲き乱れる草花の間を飛び回っているわけです。
春という穏やかな気候の中で繰り広げられている、躍動感あふれる追いかけっこ、といった感じです。
追う猫も、追われる蝶も必死のはずなのですが、「くんずほぐれつ」とあるのを見るかぎり蝶もまた楽しそうに猫と遊んでいるかのようです。
陽炎に くいくい猫の 鼾かな(宝井其角)
この俳句の季語は陽炎で、季節は春です。
暖かく、風のない日に陽炎がおこると遠くのものがゆらゆらと動いてみえます。
そんな野原で「くいくい」と音がしています。
なんだろう、と思いあたりを見渡すと、猫がいびきをかいて寝ていた、という情景が描かれています。
猫も鼾をかきますね。
鼻を鳴らすというか。
のんびりとした春の陽気に、鼾をかいて寝ている猫。
それを見ている人もまた眠気を払いきれずにいます。
「春眠暁を覚えず」―という気分がよく出ている俳句です。
内のチョマが 隣のタマを待つ 夜かな(正岡子規)
この俳句には一見季語がありませんが、無季俳句ではなくて、春の季節になります。
チョマがタマを待っている、とは逢引のために待っているのでしょう。
恋仲になったタマがやってくるのを待っているのです。
「猫の恋」とは春の季節を表す季語にあります。
ここでは直接の季語としては使われていませんが、同じことです。
なんとも自然体すぎて、これが俳句なのかなと首をひねってしまいたくなります。
俳句も和歌も文字通り息をするように詠みあげる、正岡子規らしい俳句です。
実際の春の一夜の情景とチョマが待ち焦がれている様子がはっきりと見てとれます。
実際には猫の発情期は春限定ではないのですが、昼夜となく恋する猫の鳴き声が聞こえてくるのは、この春季に似つかわしいとされています。
いなずまの 野より帰りし 猫を抱く(橋本多佳子)
この俳句の季語は稲妻、季節は秋になります。
遠くの空に稲妻が光ると、やや遅れて雷の音が鳴り響きます。
光速と音速の差による現象です。
その中を、野原に出ていた猫が帰ってきたというのですが、砂ぼこりにまみれたまま雷鳴におどろき毛を逆立て帰ったような様子が目に浮かんできます。
場合によると、縄張り争いだったり雌猫のとりあいだったりで、猫どうしの決闘に及ぶこともあり、傷ついて帰ってくることもあります。
あるいは、出かけたまましばらく戻らなかったのかもしれません。
いずれにせよ、稲妻が光る中、帰ってきた猫を抱きあげたところに俳句の焦点が結ばれています。
飼い主の心配が安堵にかわった瞬間だと感じられます。
猫下りて 次第にくらく なる冬木(佐藤鬼房)
この俳句の季語は冬木、季節は冬です。
猫が庭木に登って日向ぼっこでもしていたのでしょう。
日が傾くにつれ暖かかった外気も次第に冷えてゆきます。
それで潮時と降りてきた猫なのでしょうが、ここでは「猫下りて次第にくらく」と、逆のとらえ方をしています。
詠み手が家の中にいるのでしょう、外気にふれていないため、猫の姿がなくなったことの次に陽が沈み暗くなってきたと視覚だけが表現されています。
猫はどこにいってしまったのか、非常に気になりますが、もしかしたら飼い猫ではなく野良猫だったのかもしれません。
猫の眼に 海の色ある 小春かな(寺田寅彦)
この俳句の季語は小春、季節は冬です。
小春なので、立冬をすぎたあとの春のように温かな晴天を言います。
穏やかな日差しにおもわず冬であることを疑いたくなりますが、本当の春は厳しい冬の寒さを乗り越えた先にあります。
その猫の目には、海の色を思わせる青みがかった色がある-ということを詠んでいるのです。
猫の目は年中変わらないはずなのに、なぜ小春を合わせたのかという点はハッキリしません。
それでも、猫の目の碧さをもっとも強く感じるのに良い季節だという感覚は、分かる気がします。
飼い猫の目をのぞき込んで、その色がもっともふさわしい季節はいつだろうか、などと感じてみるのも楽しいだろうと思います。
猫にまつわる俳句を詠んでみよう
以上、猫の登場する俳句8句をご紹介しました。
こうしてみると、いかに猫が人間の暮らしに溶け込んでいて、その生活に彩りをあたえているのかが分かります。
家につくと言われる猫ですが、猫のいる情景は確かに家という存在を軸にしているんだなぁと、強く実感できますよね。
猫を詠んだ俳句は、なんだか猫そのもののように愛嬌があったり、躍動感であふれていたりします。
身近な存在なだけに、猫が詠まれた俳句もまた身近に感じることができます。