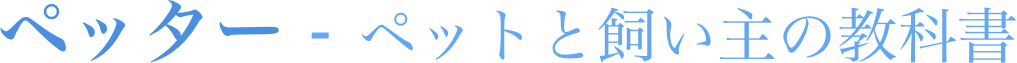ふとアゴ辺りに黒い物質に、びっくりすることがあります。
通称アゴニキビと言われるこの症状、放置すると更に状況ぐ悪化する場合もあります。
そうなる前に、原因や日々の生活で見直せる点などをご紹介します。
水が汚い
まず初めに考えられるのは、水が新鮮でないことです。
猫によっては上手く舌で水が飲めずに、アゴが水面についてしまうことも多く、注意が必要です。
循環し、濾過するようなタイプではなく、容器に水を張る場合は、最低でも1日に1回は水を新鮮なものに入れ替えてあげましょう。
見た目に濁りやゴミなどで汚れていなくても、時水分補給の度に、口周りに付いた食べかすなどで水は汚れています。
また時間の経過や、夏など高温の状態では、水質が悪化してしまい、その汚れた水によって、アゴにバクテリアが繁殖してしまい、アゴニキビの要因の一つになってしまいます。
上手く毛繕い出来ていない
猫がアゴを手入れする場合、鼻周りや上アゴの様に舌が届かない為、前脚に唾液を付けて手入れしなければなりません。
猫によっては毛繕いが上手く出来ない子もいるでしょう。
そういった場合、上手く水が飲めずに、アゴに水に浸ってしまったまま放置したり、食事の後食べかすが残っていたりすると、雑菌が繁殖してしまいます。
また水分補給や食事だけでなく、涎が原因でアゴが乾かず不衛生になることも考えられます。
そのような不衛生な状態が続くと、アゴニキビが出来、引っ掻いて悪化してしまうこともあるので、要因になり得る初期段階で手を打ちたいところです。
気になる場合は、代わりに優しく温かいタオルで拭き上げして手伝ってあげるのも良いので、是非試してみてください。
容器が合ってない
次に水入れや、食事に使用している容器についてですが、素材的に避けるべきものもあります。
その中の一つにプラスチックが挙げられます。
プラスチックは構造上目に見えない小さな穴がたくさん空いている為、バクテリアが繁殖しやすく、アゴに付着してしまうので注意が必要です。
また水を器から上手く飲めない子には、器でなく給水ポンプを試してみてください。
給水ポンプから上手く飲めるようになれば、アゴを水分補給の度に濡らさず済みます。
そのような容器の見直しに加え、毎回使用したら洗って乾燥させるなどして、衛生面も見直しましょう。
洗う時も、ただ水で洗い流すだけでなく、スポンジ等で汚れをしっかり除去し、また毎回乾燥が難しければ、容器を2種類用意し交互に使用するなど工夫しましょう。
そして最後に長時間食べ残しが容器に残ってしまうのを防ぐため、猫を観察して適量を把握し、エサを与えることも大切です。
食べ物が合っていない
エサを変えた際、エサに含まれている成分が体質に合わなかったり、ストレスや加齢により体質が変化する事で、食べ慣れたエサでもバランスが変化し、皮脂が過剰分泌されることがあります。
それがバクテリアの繁殖を手助けすることになってしまいます。
また安価なエサや、保存状態に問題があった場合も、同様に皮脂を増加させることに繋がることがあります。
皮膚の乾燥やかぶれなど防ぐ皮脂を分泌する脂腺は、まぶた、あご、しっぽの付け根、唇など数多くありますが、発見されるものの多くはあごの下であり、他の箇所に比べ、食べ残しや様々な要因が重なり発生し易いのです。
また体質の変化により、食べ慣れたエサでもアレルギー反応を起こし、アゴニキビを引き起こしてしまうこともあるため、体調が優れない時はもちろん、エサに口を付けない、大量に残すなどのサインがあれば注意が必要です。
アゴニキビが急に増殖した場合は、そういった要因も疑ってみましょう。
ストレス
繊細な猫は、ストレスがアゴニキビを始め、様々な病気の引き金になることが多いと言われています。
ストレスの中でも、引っ越しや、新しい家族が増えるなどの環境の変化によるストレスは、猫にとっては大きなストレスになりかねません。
またはそういったストレスに加え、去勢や避妊によるホルモンバランスの乱れ、加齢による体質の変化、季節によって精神状態が変化することもストレスを増大させてしまう原因になります。
アゴニキビができ、ストレスが原因だと疑われる場合には、安心出来る環境を作ってあげたり、優しく話しかけスキンシップの時間を多く設けたりするなど、原因別にストレスを緩和してあげることが大切です。
まずは原因を見つけることから始めよう
アゴニキビには様々な原因が考えられますが、早期に気付いてあげることで、症状が改善されたり、再発対策や悪化を防ぐことも出来ます。
早期に気付いてあげる為には、日々のスキンシップが欠かせません。
毎日猫に触れスキンシップを取ることで、精神状態から身体や心の変化、サインを見過ごさないようにしてあげたいところです。
まずは猫を観察することで変化に気付き、ストレスを取り除いたり、日々のお手入れや、容器食べ物を見直したりして、予防していきましょう。