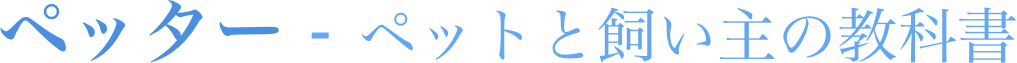犬は古来より、人間の暮らしになくてはならない存在でした。
最も古い時代からの人類の歴史のペットとして、暮らしに狩りに犬は人の役に立つだったのです。
その犬は、俳句の中でも頻繁に詠まれてきました。
今回は、犬の登場する俳句をご紹介します。
犬が来て 水のむ音の 夜寒哉(正岡子規)
季語は夜寒で、季節は冬です。
暖房もろくにないこの時代。
冬の寒さは容赦なく部屋に押し寄せてきます。
そんな季節に夜も更けて、なにやら庭の方から音がします。
何の音だろう…?と耳を澄ましていると、気配や物音から犬のようだと分かります。
その水を飲む音だけが、寒い冬の夜に響いています、という俳句です。
いまは室内犬が増えましたが、昔は犬といえば庭で飼うのが一般的でした。
こんなふうに犬が水を飲む音が、冬という季節にさらに彩りを与えているのです。
犬が来て 覗く厨の 春の暮(山口誓子)
季語は春の暮で、季節は春です。
似た季語に暮の春があります。
暮の春は春の終わりをさしますが、春の暮は春の夕方を意味しています。
厨というと古風な感じですね。
犬がふらっとやってくるわけですから、古民家の土間にあるような台所なのかもしれません。
その厨へ犬がやってきて覗き込んでいる、というのです。
飼い犬か野良犬か、覗き込んだ理由は小腹が減ったのか、あるいはただなんとなくだったのか、その辺りはハッキリしません。
ただ、春の夕暮れに犬が台所を覗き込んでいるという一情景があるのみです。
それだけなのに、小首をかしげている犬の姿が春の夕日に照らされて、不思議と郷愁のようなものを含んだ俳句になっています。
犬耳を 立てて土嗅ぐ 啓蟄に(高浜虚子)
季語は啓蟄、季節は春です。
春になり、冬眠していた虫たちが穴から地表に出てくる節季のことで、3月5日頃になります。
散歩中の犬でしょうか、その野の土を嗅ぎ回っています。
その犬の耳がピンと立っていたという句です。
冬の寒さを越え、春を迎えた喜びが聞こえてきそうではありませんか。
世は、生命溢れる春になった。
その春の野を、犬が耳をピンと立てて匂いを嗅いでいるのです。
春の土は、実際におだやかな陽光に温められて、仄かな命の香りを含んでいます。
こうしたことは、犬を連れて野を散歩しているとよく実感できるところです。
こほろぎや 犬を埋めし 庭の隅(正岡子規)
季語はこほろぎ、季節は秋です。
飼い犬が亡くなって、庭の隅に埋めました。
ちょうどその辺りからこほろぎの鳴き声が聞こえている、という情景です。
ペットが亡くなって、ぽっかりと心に穴の開くことをペットロスなどと言います。
人の命の方が長いことなど承知の上でペットを飼う。
とはいえ、連れ添った時間の長さが、慈しんだ瞬間の数々が、飼い主の心にさまざまな悔いを生みます。
しかし、確かなことが一つあります。
愛された動物たちは、幸せな生を得たということです。
そして飼い主の元気な姿を見たいと望んでいるだろうことです。
こほろぎの鳴き声をもの悲しいと感じることもできるのですが、こほろぎにとってその声は生を歌うものであるはずです。
命を全うした動物たちに負けず、飼い主もまた自分の命に向き合わなくてはなりません。
里の子の 犬引いて行 枯野哉(正岡子規)
季語は枯野で、季節は冬です。
草も枯れ尽くした野を、里の子が犬を散歩させています。
この俳句だけで、里の子と犬との歩く位置関係がわかります。
「里の子の犬引いて」というからには、犬が四肢をつっぱって前のめりに進んでいるのではありません。
里の子が前、犬は後ろを歩いています。
また、枯野を行くわけですから、あまり急いでもいません。
「引いて行」くわけですから、目の前を通り過ぎた子供と犬は、徐々に遠ざかり、小さくなってゆきます。
おだやかな冬晴れの陽光の中、いつまでもその姿を見送っています。
水うてば 犬の昼寝に とヾきけり(正岡子規)
季語は水うてば(打ち水)、季語は夏です。
夏の暑い日、飼い主が打ち水をしていると、昼寝をしている犬にまで届いてしまった、というのです。
打ち水ですから、たいていの場合、時間帯は正午前くらいでしょうか。
犬も暑気に困って地面に穴を掘り寝そべっていたのかもしれません。
打ち水が犬のどの辺りにかかったのか、どの程度の水を被ったのか、その辺りは読み取れません。
しかし、のそのそと起き上がり、身体を激しく揺すって水滴をとばしている犬の様子が目に浮かんできます。
古犬が 先に立也 はか参り(小林一茶)
季語は墓参り、季節は秋です。
墓参りは格別季節の行事というわけではありませんが、季語としての墓参りは盂蘭盆のそれを指しています。
おそらくは毎年その墓参りに行くために犬も条件反射のように動いているのでしょう。
勝手を知った古犬が人間を先導してゆく様は滑稽というかしみじみとしたおかしみを含んでいます。
また、古犬のこれまでの飼い主との関係性が伺えるようでもあります。
ともに墓参りをするのは誰の墓か、古犬もよく知っている人物の墓だろうということも言えそうです。
木犀の 香や純白の 犬二匹(高野素十)
季語は木犀で、季節は秋です。
中秋のころ、路地などを歩いていると、たまらなくいい香りが漂ってくることがあります。
橙色の小さな花は金木犀、白色の小さな花は銀木犀とよばれます。
思わずその場に立ち止まってしばらく留まっていたくなるような、そんな香りです。
そこに純白の犬が二匹佇んでいます。
犬は人間などとは比べ物にならないくらい嗅覚が優れていますから、人間と同じように木犀の香りに引き寄せられているに違いありません。
まったく異なる種類の生き物同士でありながら、こうした共通の趣味というか志向をもっているというところに、長い時間人と犬とがともに暮らせてきた背景があると言えそうです。
犬にまつわる俳句を詠んでみよう
以上、犬の登場する俳句8句をご紹介しました。
われわれ人間にとって犬はもっとも古い時代からのパートナーでした。
犬という存在があるだけでどこかホッとするのは、そうした歴史的な背景が遺伝子レベルで人間の感覚の中に溶け込んでいるからかもしれません。
犬を詠んだ俳句がよく伝わってくるのは、それだけ犬が人間にとって近しい存在であることの証明だと言えるでしょう。