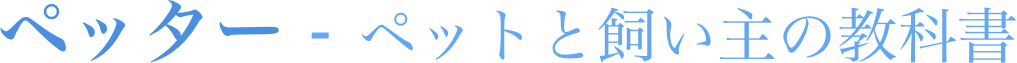マラセチアは細菌性の皮膚炎に次いで、非常に多い皮膚疾患です。
体質としてマラセチアによる皮膚炎を繰り返してしまう犬も少なくありません。
ここでは、マラセチアの症状や原因、治療法についてご紹介します。
マラセチアの症状
皮膚の痒みや赤み、べたつきを特徴とする皮膚疾患で、特に脇や股に症状が出ることが多いです。
また、マラセチアが原因の外耳炎が起こることも非常に多いです。
茶色っぽい、べたっとした耳垢が見られます。
皮膚炎の場合も、外耳炎の場合も、甘酸っぱいような独特の香りが特徴的で、日本ではシーズーに多く見られます。
その他にも、フレンチブルドッグやパグ、コッカースパニエル、ウエスティーなどの犬種でも繰り返すことが多いです。
暑い季節に悪化・発症することが多く、梅雨から夏にかけては要注意のシーズンです。
若い年齢の犬~高齢の犬まで幅広く発生が見られ、慢性経過を辿ると皮膚が象の皮膚のように厚く肥厚したり、脱毛したり、色素沈着といって皮膚が黒く変化したりすることも少なくありません。
マラセチアの原因
マラセチアは元々皮膚に常在するカビの一種です。
いわゆる酵母菌でダルマのような形をしています。
マラセチアは皮脂を好むので、皮脂の多い犬種や皮脂の分泌が増えるとマラセチアも増殖しやすくなってしまいます。
そのため、前述のように蒸れやすい梅雨から蒸し暑い夏にかけては悪化することが多いです。
マラセチアは、そのものが過剰に増殖して炎症を起こすこともありますが、アレルギーのように増殖したマラセチアに反応して皮膚炎が起こることもあります。
また、マラセチアとともに細菌も増殖し、皮膚炎が悪化することも多く見られます。
マラセチアが過剰に増殖する時には、基礎疾患としてアレルギー疾患のような皮膚のバリア機能の低下を起こす疾患や、免疫力を低下させるホルモン疾患が存在することもあります。
治療をしてもなかなか全身性の皮膚炎が良くならない時には、基礎となる病気を疑う必要があります。
マラセチアの治療法
マラセチアの診断は、動物に負担のない方法で行うことができます。
セロハンテープを皮膚にぺたぺたとくっ付け、それを染色し、顕微鏡で観察する方法です。
もしマラセチアが増殖していれば、セロハンテープにくっつくので、「本当にマラセチアによる皮膚炎なのか(細菌性の皮膚炎ではないのか?)」ということがわかります。
所要時間もさほどかからず、判断をつけることができます。
動物も痛がる検査ではないので、飼い主さんも気楽に検査に臨むことができるでしょう。
また、治療方法は下記のとおりです。
シャンプーを行う
まず、シャンプーをすると、物理的にマラセチアを落とすことができます。
そして、マラセチアを殺す薬用成分が含まれる薬用シャンプーを使用すると、より効果的になります。
飲み薬を飲むよりは体への負担も少なく済むところが、シャンプーによる治療の優れているところです。
薬用成分の入ったシャンプーを使う時には、泡立てた状態で5~10分間放置することでさらなる効果が望まれます。
犬の気を逸らしながら、頑張ってください。
ご家庭でシャンプーをするのが難しいようであれば、ドッグサロンや動物病院併設のトリミング施設に依頼することをオススメします。
ただ、頻度が1週間に1回から2回と高頻度でのシャンプーが必要になるので、ご家庭でシャンプーができると経済的な負担も少なくて済みます。
シャンプーは必ず、動物病院で処方された犬用の商品を使いましょう。
マラセブシャンプーという商品が最も有名な商品です。
シャンプーの行い方や実施頻度は獣医師の判断に従いましょう。
飼い主さんの判断のもと行うと、逆に皮膚炎が悪化してしまうことがあります。
抗真菌薬を飲む
飲み薬によってマラセチアを殺す治療法もあります。
マラセチアによる全身性の皮膚炎であるとき、病状がひどい時、シャンプーができない時に選択されることがありますが、飲み薬なので、体への負担も少なくありません。
また、価格が高いことも、この治療法のデメリットです。
シャンプー療法と飲み薬を併用することも多いです。
外用薬を使用する
マラセチアに効果のある外用薬(=塗り薬)もオススメです。
ただ、皮膚炎が全身の時には塗るのが難しいので、局所的な場合に選択されます。
しかし、飲み薬ほど体への負担がないのがメリットです。
外耳炎の時には、直接耳に垂らす点耳薬が使われます。
マラセチアを治そう
マラセチアはどの犬も一生で一回は患うことのある病気と言っても過言ではない病気です。
放っておくと、皮膚炎は悪化し、どんどん悪循環に陥り、治りにくくなってしまうことが多いです。
そのため、赤みや痒み、べたつきを感じたら、早急に動物病院を受診することをオススメします。
また、体質として皮脂の分泌が多く、皮膚炎が慢性化して、飼い主さん自身も諦めてしまうことも少なくありません。
でも、そのような場合は一度皮膚の専門医、もしくは認定医の診断を受けてみてはいかがでしょうか。