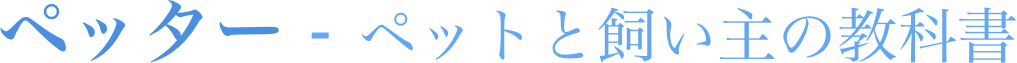オカメインコは身体が大きい反面、性格は甘えん坊の面と臆病な面を持つ鳥であり、可愛いペットとして人間を癒してくれる点では最適の鳥と言えます。
寿命も15年から25年と長く、体調管理をしっかり行えばさらに長い間を一緒に過ごすことができる鳥です。
今回は、そんなオカメインコの性格や特徴をご紹介します。
人に慣れやすい
オカメインコは人にすぐ馴れる性格ですので、通常のインコのようにヒナから育てなくても、手に乗せたりして馴れさせることができます。
さらに「甘えん坊」、「まったり」という表現がぴったりな性格です。
手に乗っても強く噛んだりせず、長く肩に止まっていたり、髪の毛の中に頭を入れて、いわゆる髪浴びを行ったり、自分から頭を掻いて欲しいとねだったりするというような癒しの性格を持っています。
鳥かごから出した時に床の上を歩くことも好きなので、その歩く姿も癒しを与えてくれます。
小さなお子さんがいる家庭でも問題なく飼うことができるのでオススメです。
同じく、他の鳥と同じ鳥かごの入っても仲良くできケンカすることもありませんが、いじめられる場合がありますので、よく観察していることが大事です。
神経質な一面もある
穏やかな性格である反面、「臆病者」、「寂しがり屋」という一面も持っています。
野生で生活している時には集団で生活しているため、どうしても単独で生活している場合は寂しがり屋の性格が出ると言われています。
特に有名なのはオカメパニックと呼ばれている行動ですが、ちょっとした物音が夜中に聞こえると鳥かごの中で暴れて飛び回ることがあります。
ひどい場合は羽を折って負傷することもありますので、オカメパニックになった時は、優しく声をかけてあげることをオススメします。
夜中も少し明かりをつけておくことはパニックの予防になります。
稀に、外を飛んでいる鳥を見てオカメパニックになることもあります。
このような性格から、出来るだけ複数で飼う方が落ち着きやすいということになります。
また、飼い主さんの扱い方に対しても敏感に感じる所がありますので、粗雑な飼い方、接し方をすると飼い主を怖がり、今まで築いてきた信頼していた関係がなくなってしまうこともあります。
口笛上手
セキセイインコほどのレベルではありませんが、オカメインコの雄はしゃべるのが上手です。
特に機嫌の良い時には、長い単語ではなく短い単語であれば覚え、音を真似ること、口笛を吹くことができます。
自分の名前を覚えさせる練習を続けて、飼い主とコミュニケーションと信頼関係を築くこともできます。
うまくなれば、手の上で目を合わせて歌を覚えさせることもできるので、両者とも歌の練習をワクワクしながら楽しめます。
呼び鳴きには注意
飼い主さんがいなくなった時に、口笛で甲高い大きな声で鳴くことがあります。
これを「呼び鳴き」と言いますが、寂しがり屋の性格から来る行動で、かまってほしい・遊んで欲しいという表現です。
特に雄は発情期となる春を迎えると、一段と大きな高い口笛のような声を出します。
隣近所まで響くほどの高い音ですので、マンションなどで飼う場合は特に注意が必要です。
一方、雌は鳴く声も静かで、おっとりとした性格であると言えます。
オカメインコの体の特徴
飼う鳥の中では大型の分類に入りますが、インコの中では中型に分類されます。
身体の長さは30cmから35cm程度であり、長い尾の羽が身体の長さの半分を占めます。
特徴的なのは、頭の上の冠毛と赤らめた頬であり、この頬が「おかめ」に似ていることから「オカメインコ」の名前の由来と言われています。
但し、頬が赤くないオカメインコの種類もいます。
この赤さも雄は成長していくうちに消えてしまうのが特徴です。
冠毛は逆立ち状態の時と、ペタリとなっている状態でその時の気分を表しています。
指は前と後ろにそれぞれ2本ずつに分かれており、物をしっかりと掴むために良く出来ています。
歩き方も鳥の中では珍しく、ヒトのように片足ずつしっかりと交互に歩きます。
糞の色は健康状態であれば、緑色・茶色に白色がついている固まり状になっています。
また、緊張すると糞の量も増加し、水分を多く含むようになります。
オカメインコを飼ってみよう
オカメインコは頭が良く、根気良く訓練すればおしゃべりも歌も覚えることが出来ます。
また、あくび・毛繕いなど可愛いしぐさ見ていると、私たちに癒しを与えてくれペットとしては最適の鳥です。
オカメインコの性格と特徴をしっかり理解して、楽しいコミュニケーションを続ければお互いにワクワクしながら生活を送れますので楽しんで下さい。
寿命は15年から25年と長いですが、オカメインコの1歳が人間でいうと18歳に相当しますので繁殖は可能となります。
野生の鳥は敵から自分の弱みを隠そうとして、自分の弱みを見させない所がありますので、普段と違う行動・体つきになった場合にはすぐに適切な対処をして、場合によっては動物病院へ連れていくことが必要です。